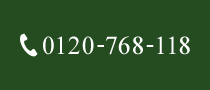口腔の粘液嚢胞(mucocele)とは
口腔内にできる粘液嚢胞(mucocele)は、唇の内側や頬の粘膜などに突然プクッと生じる水ぶくれのような状態を指します。粘液停滞嚢胞ともいいます。唾液が粘膜内に閉じ込められることで発生し、白っぽく半透明な見た目とやわらかい感触が特徴です。原因として多いのは、唇を噛んだり頬の内側を傷つけたりといった外的刺激で唾液腺やその導管が損傷し、唾液が周囲に漏れ出してしまうことです。とくに若い年代での発生が目立つものの、子どもから大人まで幅広い年代で起こり得る病変といえます。
下唇の内側や頬の内側、舌の裏、 口の底などによく見られます。
粘液嚢胞の症状と日常への影響
粘液嚢胞そのものは痛みを伴わないことが多いのですが、大きくなると咬み合わせの際に邪魔になり、さらに噛んでしまうことで悪化する可能性があります。日常生活においては食事や会話の際に違和感が生じやすくなります。表面が破れると一時的に小さくなることがあっても、唾液腺や導管の損傷箇所が癒合していない限り、再発するケースも少なくありません。
粘液嚢胞の原因
繰り返す外傷や癖(唇を噛むなど)や軽い慢性炎症が原因となって、唾液腺の排泄管が損傷して唾液が漏れ出たり、唾液腺の排泄管が詰まって唾液がたまることで発生します。
唾液腺には顎下腺、耳下腺、舌下腺という大唾液腺以外にも、唇や頬の粘膜に小唾液腺というものがあり、この小唾液腺からも粘液嚢胞が生じることがあります。

粘液嚢胞の治療法
まず歯科医院や口腔外科を受診して、嚢胞の状態を正しく診断してもらうことが第一です。
粘液嚢胞は通常は積極的な治療を必要としませんが、大きさや症状によっては治療が必要になることもあります。
特に大きくなった粘液嚢胞や何度も再発を繰り返すものは、外科的な切開により嚢胞内部の排出を行い、必要に応じて唾液腺や導管を摘出します。軽度であれば経過観察と自然治癒を待つ場合もありますが、悪性疾患などとの鑑別が必要なため、専門家の判断を仰ぐのが安心です。
日常生活で気を付けたいセルフケア
口腔内を清潔に保ちながら、誤って唇や頬を噛んでしまわないよう食事の際はゆっくりよく噛むことを心がけましょう。口腔内に不安な症状があれば、自己判断でつぶしたり放置したりせず、歯科医院へ相談することが大切です。ストレスや疲労が溜まっている時には、十分な休息を取りながら体調管理にも気を配ると良いでしょう。

まとめ
粘液嚢胞は良性の病変ですが、再発を繰り返す場合は治療が必要になることもあります。
唇を噛む癖があるなどといった場合は、それが解消されるように努めましょう。
気になる場合はご相談ください。
京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善